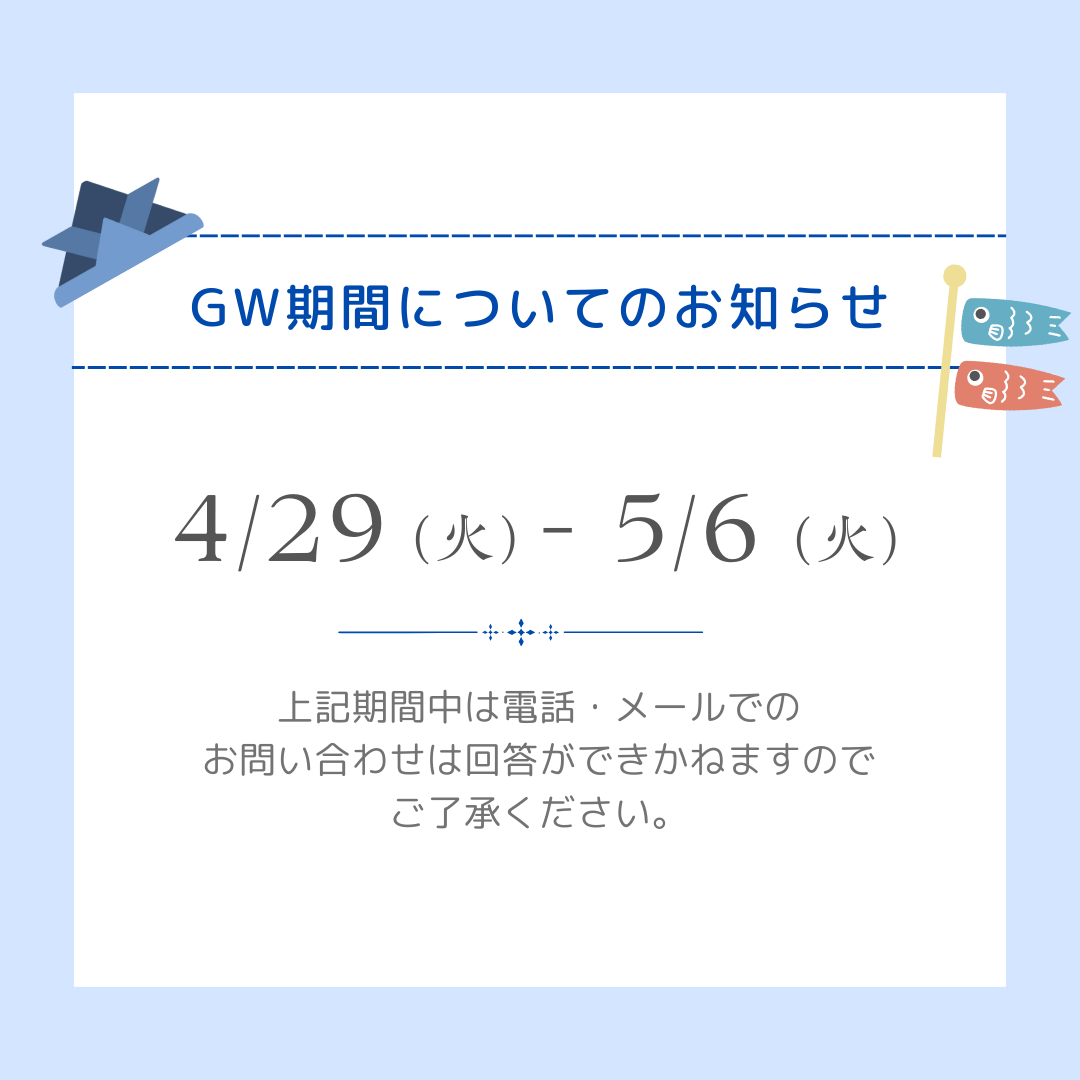- 通学部/学科一覧+-
2022/11/08
こんにちは!日本福祉教育専門学校です。
今回は社会福祉士国家試験で2025年2月受験から内容が反映されることになった新カリキュラムについて、その中身をわかりやすく説明します。

新カリキュラムの中身をご紹介する前に、まずは社会福祉士について説明します。
社会福祉士の仕事は、仕事と職場と職種によって多岐に渡りますが、わかりやくお伝えすると「日常生活を送ることが困難な方を、福祉の面から支える役割」です。
困っている方の相談に乗ったり、福祉面から支援やアドバイスをしたり、医療保健分野とも連携して橋渡しをする役割もあります。
そのため、社会福祉士が支援する対象者は幅広く、高齢者・身体障害者・知的障害者・家庭・子ども・低所得者などを支援します。
なかでも、精神障害者に特化した専門職が精神保健福祉士となります。そのため社会福祉士と精神保健福祉士は国家試験科目でも共通科目が多いのです。
社会福祉士を目指すには国家試験を受験して合格しなければなしませんが、この国家試験の受験資格として社会福祉士養成課程(大卒であれば1年制の通学課程など)を修了する必要があります。
今回話題となっているのは、この社会福祉士養成課程でのカリキュラム改定です。これを業界では「新カリキュラム」と呼んでいます。
そもそもどうして2025年2月受験の国家試験から新カリキュラムの内容が反映されることになったのでしょうか。その背景には国の目指す「地域共生社会」の実現があります。
日本では少子高齢化が進み、社会も複雑化するなかで、LGBTなどのマイノリティの支援、80代の親がひきこもりの50代の子ども支援する8050問題、外国人労働者の生活支援など、さまざまな支援すべき課題が出てきています。このような社会状況の中で社会福祉士の活躍の場は広がってきているのです。
その一方で、社会福祉士の養成カリキュラムは2007年に見直しをしてから、10年以上見直しがされてきていませんでした。
そしてこのたび地域共生社会の実現の中心的な役割を担う社会福祉士は、その養成カリキュラムが見直しをされ、「新カリキュラム」として、2025年2月受験の国家試験から変わります。
社会福祉士の国家試験は、福祉専門職の試験の中でも最難関と言われることが多いです。
それは年1回しか実施しない社会福祉士国家試験合格率の全国平均が30%前後のためです。
10名受験してもおおよそ3名しか合格できないということになります。
ほかの福祉専門職と比較しても、精神保健福祉士国家試験では約60%、介護福祉士国家試験では約70%の合格率と比べても、狭き門と言えるでしょう。

新カリキュラムと旧カリキュラムではさまざまな見直しがされていますが、ここではおもな3つの変更点についてご説明します。
旧カリキュラムの科目名であった「相談援助」という言葉はなくなり、「ソーシャルワーク」という言葉が使われるようになりました。
これは、これまでの個別の相談援助の仕事がメインではなく、より幅広く活躍できる人材に育成することを表しています。
社会福祉士がこれからさらに地域共生社会を構築する役割を担うために科目が新設されました。
この科目では、地域福祉の考え方から多職種連携、地域ネットワークを構築するために必要な知識などを学びます。
実習の名称は「相談援助実習」から「ソーシャルワーク実習」に変更します。
そして、これから社会福祉士を目指そうとする社会人の方にいちばん影響がありそうな変更内容が時間数と実習先の追加です。
具体的には、実習時間数が180時間→240時間以上に60時間増えます。
さらに実習先も1か所以上だったところが、2か所以上の事業所・施設・相談機関で行うことになりました。
カリキュラムの変更はこれから社会福祉士として活躍するうえではとても有益な学びとなりますが、実習時間数が増えることによって、働きながら学ぶ社会人にとって、これまで以上に職場の理解が必要となります。
社会福祉士の活躍できる場所は、福祉施設・児童相談所・学校・地域包括支援センターなど幅広く、高齢化が進むなかでは高齢者向けの施設での需要が高まり、学校ではスクールソーシャルワーカー、虐待などの社会問題では児童相談所などさまざまな分野で必要とされていて、需要は高まる一方です。
国家資格ということもあり信頼性の高い資格であり、これまでの経験を活かしつつ社会人からの学び直しをする層も多いことも特徴です。

社会福祉士の仕事は社会貢献度も高く、やりがいのある仕事です。これまでのキャリアを活かして、生涯活躍できる仕事として活躍することが可能です。

合格者数全国1位。
1年制の最短コースで社会福祉士国家資格を取得できます。

合格者数全国1位。
土日休みの「週休2日制」のコースと18:10授業開始の2つのコースから選べます。